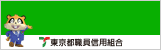【清掃作業の特徴】

清掃事業は「収集・運搬・処理・処分」を基本とし、「収集・運搬」を各特別区が、「処理」を清掃一部事務組合が、「処分」を東京都が行っています。
各区で数万か所となっている集積所からごみや資源を収集し、それぞれ適正な処理施設に搬入しています。幹線道路から狭小路地、大型マンションからの収集や各戸収集など、各区の特性や地域性などに応じて収集車や収集形態を変え、安全な作業による確実な収集を目指しています。
また、ごみ出しが困難な高齢者や障がい者に対する戸別訪問収集も実施しており(条件あり)、きめ細かいサービスも展開しています。
【安全で安定的な清掃工場】

清掃工場の設備には、ごみを燃やす焼却炉、焼却炉にごみを投入するクレーン、排ガス中の粉じんを取り除くバグフィルター、排気ガスを洗浄・中和する洗煙装置、汚水から有害物質を取り除く汚水処理設備など、様々な機器があります。これらの設備が1ヶ所でも停まれば、正常な清掃工場の運営はできなくなります。安全で安定的な清掃工場を運営するため、365日昼夜を問わず複雑な機械の制御を行っています。
【未来にむけた啓発事業】

清掃事業には、環境行政と密接な関係となる「ごみ減量」や「CO₂削減」などの大きな課題があります。また、最終処分場(埋立地)には限りがあり、「ごみ減量」は喫緊の課題です。ごみの減量や資源化を推進するため、収集時の対応だけではなく、小学校や保育園・幼稚園への環境学習(出前講座)を実施しています。
分別クイズ、パネルシアター、演劇、収集体験などを交え、子どもたちが興味・関心を持てるような工夫を凝らし、『分別の大切さ』や『ごみを減らす方法』を伝えています。
【大規模自然災害時の対応】

阪神・淡路大震災における廃棄物処理支援を皮切りに、これまで多くの被災地支援に取り組んできました。
災害の種類によって災害廃棄物は形状・量が変わり、被災した自治体の体制によっても求められる支援が変わります。被災した住宅から排出されるごみの収集、仮置き場からのごみの運搬、困難な状況に陥った通常収集の応援、避難所のごみの収集など、業務は多岐にわたります。
また、2019年には大田区・世田谷区において台風の影響で河川が氾濫し、浸水被害による災害廃棄物が集積所へ大量に排出される事態となりました。私たちは現場で培ってきた経験とともに、これまでの被災地支援の経験も踏まえた迅速な対応により、住民から感謝される一幕もありました。